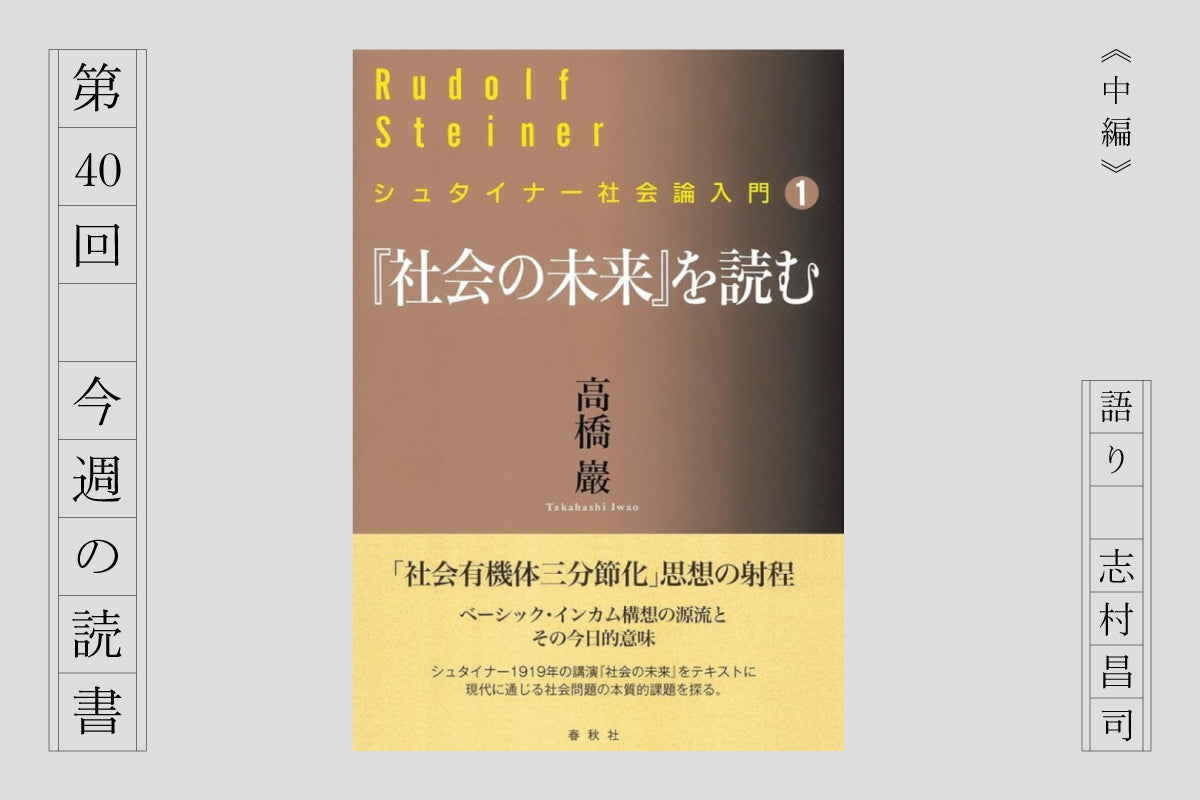
『社会の未来』を読む』《中編》
今週も引き続き、高橋巌さんの『「社会の未来」を読む』を取り上げます。この本は、シュタイナーが1919年に行った講演『社会の未来』を、高橋巌さんが読み解いた講演集です。
前編はこちら
「社会適応」から「私の中の社会」へ
前回は「社会衝動」について触れました。社会論を考える上での基本的なスタンスは、「社会適応」の問題ではない、という点がまず出発点としてありました。
「社会適応」とは、既存の社会を前提として、子どもや若者が、いかにその社会に自分を適応させるかという問題です。シュタイナーの社会論はそのようなものではない、というのが彼の議論の出発点です。
それを高橋さんは「社会の中の私」という言葉でまとめています。「社会の中の私」という社会論ではなく、「私の中の社会」こそが重要だということです。つまり、一人ひとりの中にある「社会衝動」を形にしていく。この社会衝動とは、この世に生まれた人は誰でも、「本来こういう社会で生きたい」「こういう自分でありたい」という願いを持っているはずだ、ということです。
今の私たちは、自分の中にある社会衝動を忘れた状態にあります。私たちの内面を深く掘り下げていくと、その根底には、本来私たち一人ひとりが持っている「あるべき社会を求める衝動」、すなわち社会衝動が眠っている、というのがシュタイナーの基本的な考え方です。
もちろん、社会衝動は一人ひとり異なります。そのように一人ひとり異なる社会衝動が相互に作用し合い、合わさることで、全体として一つの社会が形成されていくというのが基本的な考え方です。これから、一人ひとりの社会衝動に基盤を置いた社会論が、どのように展開されていくのかを見ていきます。
現代社会の課題①:経済中心主義の弊害
その話の前に、現代社会がどのような社会になっているかについて、高橋さんは問題を提起しています。
一つは、現代社会では精神生活よりも経済生活が上位にあり、経済生活が社会の土台(下部構造)になっているということです。この経済中心の社会では、お金がすべてを支配するようになってきています。以前よりも、貨幣や資本の持つ力がますます強くなっているとも言えるでしょう。
そのような中で、一人ひとりの人間の精神的な営みが、資本やお金の力から自立し得るのかという問いが生まれます。むしろ、人間の精神的な営みはすべてお金や資本に取り込まれてしまっているのが現状です。そのため、資本やお金から離れた精神的な発言は、非常にユートピア的で非現実的だ、「地に足がついていない」と思われがちです。
お金がなければ何もできない、お金がすべてになってしまったということが、現代社会の抱える一つの問題ではないでしょうか。
現代社会の課題②:労働力の商品化と人間性の否定
もう一つ、高橋さんが問題にしているのは、労働力が商品化されているということです。これは今に始まったことではありませんが、「労働力を商品として提供する代わりに、対価としてのお金をもらう」という考え方が、現代では当たり前となっています。
しかし、人間本来の「働く」というあり方を考えたとき、必ずしも自分の時間や労働力を商品として提供し、対価としてお金を得ることがすべてではないはずです。この本では、「労働力は商品ではない」「本来、貨幣で労働力を売買することはありえない」と述べられています。本来の労働は、報酬や貨幣と結びついたものではないのです。
現代では、「働くこと」と「経済生活」がほぼイコールになっています。労働力が商品化されたことによって、様々な弊害も生じています。
一つは、人間性が否定されてしまうということです。以前、ここで影山さんの著書『ゆっくり、急げ』を扱った際に、「人間の命が目的のための手段になってしまっている」という話がありました。労働力を商品として考えると、例えば資本主義においては、利潤の追求や売上が目的になります。その大きな目的に対して、個々の労働力は手段と化していくわけです。手段としての労働力は、ある意味で人間性の否定につながりかねません。
また、「労働の疎外」という言葉もあります。働き手が、働くことと自分の気持ちや感情とが乖離していく状態です。労働力を売るということは、自分自身の時間から自分が疎外され、引き離されてしまうことでもあるのです。
ですから、本来は「働く」ことと「報酬」を同一視したり、労働力を商品とみなしたりせず、切り離して考える必要があるのです。本来の「働く」ことの意味とは何なのかが、もう一度問い直されなければなりません。
ベーシックインカムという思想的実験
そうした現状の中で出てきた考え方の一つが「ベーシックインカム」です。ベーシックインカムは、「すべての人に、無条件で、一定の所得を保障する制度」と定義されます。労働の有無にかかわらず、例えば一人あたり月10万円が支給されます。二人世帯なら毎月20万円、四人家族なら毎月40万円を受け取る形です。
これは、最低限の生活が保障されたとき、私たちは一体何を始めるのか、という壮大な社会実験でもあります。ネガティブに捉えれば、一定の所得が保障されると人々は働かなくなり、社会的な活動をしなくなるという見方もあります。一方で、ポジティブに捉えれば、賃労働から解放された人々は、本来自分がしたかった活動に取り組めるようになる、という考え方もあります。
ベーシックインカムを導入したときに社会がどうなるかは、未知数な部分も多いですが、その理念には、労働を商品化から解き放ち、人間本来の労働を取り戻そうとする思想的な根源があるということは、心に留めておいてもよいでしょう。
シュタイナーの「社会有機体三分節」
現在の社会は、資本やお金が精神生活の上位に来てしまう現状から、様々な問題が起こっています。では、一体どのような社会があり得るのか、シュタイナーの議論から考えてみたいと思います。
シュタイナーが提唱するのが「社会有機体思想」という考え方です。シュタイナーは、社会を法制度や社会制度としてではなく、一つの「生き物(有機体)」として捉える点に特徴があります。
その有機体としての社会には、3つの領域(循環系)があります。1つ目が「精神生活」、2つ目が「法生活」、3つ目が「経済生活」です。
この精神生活、法生活、経済生活という3つの領域が、それぞれ自立した役割を果たしつつ、相互に調和して機能することによって、社会という一つの有機体が健全に発展する、というのが彼の考え方です。
人間の身体に、神経系、消化器系、循環器系といった様々な系があるように、社会も全体として様々な系から成り立ち、一つの生き物のように発展していくのだと考えます。この社会の未来を、3つの系を持つ有機体として考える思想を、シュタイナーは「社会有機体三分節(さんぶんせつ)」と呼びます。この具体的な議論が、『社会の未来』の中で展開されています。
三つの原理:自由・平等・友愛
要点をかいつまんでお伝えします。
-
精神生活:人間の精神活動や創造活動全般を指します。この中心原理は「自由」です。自由な思考と精神生活が最も重要な原理となります。
-
法生活:国家や政治における人々の権利関係や社会秩序を規定する領域です。この原理は「平等」です。
-
経済生活:人間の経済活動全般を指します。この原理は「友愛」です。
このように、自由・平等・友愛という3つの原理が、それぞれの領域の原理になっているとシュタイナーは説いています。
古代から近代へ:世界観の変化
この社会有機体思想を考える上で、背景となる私たちの世界観がどう変化したのか、という点に触れる必要があります。シュタイナーは、古代と近代の世界観の違いについて述べています。
古代の世界観は、人間の霊性と宇宙の霊性が結びついた時代だったと言います。人間は何よりもまず霊的な存在でした。ヨーロッパなどでも、人間の精神世界(ミクロコスモス)と、大いなる存在である宇宙(マクロコスモス)が照応関係にある、あるいは神が非常に身近な存在として人々の生活の中にありました。そうした目に見えない存在と結びつきながら、古代の人々は生きてきたのです。
そうした霊的な生活や信仰の生活を送ってきた人々ですが、15世紀、16世紀頃から様々な科学的発見があり、「脱魔術化」という現象が起こります。そして、機械論的な世界観が台頭してくるわけです。
宇宙の様々な事象も、自然法則(物理学的、数学的な法則)によって捉えられるようになると、古代の人々が持っていた霊的な感覚は失われ、世界はある種の記号として認識されるようになります。それとともに、崇敬の対象であった自然や神はどこかへ追いやられ、自然界が人間の支配の対象となってしまうという問題が起こるのです。
近代化と労働の変化
霊的な存在に満ちた世界から、単なる無機的な数式で動く機械論的な世界へ。この認識の変化と同時に、資本主義的な経済体制や近代の技術文明が台頭します。
そのような大きな変化の中で、例えば私たちに身近な「手仕事」を考えてみましょう。人間は様々なものを手で作ってきましたが、その手仕事も近代化に伴い機械に置き換えられていきます。すると、手仕事をしてきた職人たちは、工場労働者として機械を扱うようになります。このあたりから、先に述べた「賃労働」が生まれてくるわけです。
手仕事には、自然との結びつき、自然の霊的な存在と自分自身の内面との結びつきがありました。また、貨幣経済とはまったく別の次元で、物を作る喜び、自然を介して創造する喜びが、労働の対価であり、喜びそのものでした。この点を重視したのがウィリアム・モリスなどです。
それがやがて、労働の喜びや自然と人間の内面的な交流ではなく、「何時間働いたからいくらもらう」という賃労働に置き換わっていきます。これは工場労働に限らず、事務仕事でも知的労働でも、自分の時間を商品として売り、対価として貨幣をもらうという意味では同じことです。
このように、世界観の変化とともに、人間の精神生活も機械文明の中に閉じ込められていく、というのがシュタイナーの基本的な世界認識です。
精神問題としての社会問題:言葉の空洞化
そうした中で、社会論をどう考えていくべきか。シュタイナーは、社会論を制度設計や法律の改正といった問題として捉えません。社会問題を根本的に捉えようとするなら、それは「精神問題」として捉えなければならないと言います。
「精神問題としての社会問題」とはどういうことでしょうか。一つには、人間の精神活動が機械文明や経済生活に取り込まれる現状において、「言葉が空洞化」し、思想が「単なる記号」になってしまっているという問題です。
これは、かつてのマルクス主義的な言い方をすれば「イデオロギー」、現代風に言えば「ポジショントーク」のようなものでしょう。
言葉とは本来、発する人の内面と結びついており、その人の内面性と切り離せないものです。しかし、言葉が記号化してしまうと、誰が発しても辞書的な共通の意味でしか理解されなくなります。そのため、本当はもっと深い意図があったとしても、非常に浅くしか理解されません。
例えば、石牟礼道子さんは『苦海浄土』の中で、「言葉が通じない時代だ」という問題意識を示しています。また、厚生省(当時)と直談判しても、人間同士が話しているはずなのに、そこには非常に大きな隔たりがあると訴えています。
それは、水俣病患者の方々が持つ内面と結びついた魂の言葉が、記号としてしか受け取られず、言葉そのものが魂の内面を伝える力を失って流通してしまっている、という問題です。これは非常に根源的な、言葉の限界性という大きな問題だと言えます。
イデオロギー論とコミュニケーションの断絶
個人の内面性から切り離された記号としての言葉という問題に加え、イデオロギー論の問題もあります。これは、その人が発する思想や考え方も、実はその人の立場や置かれている社会状況から生まれた派生物に過ぎない、という見方です。
マルクス主義の用語で言えば、「上部構造と下部構造」の話です。下部構造である経済生活がすべてを規定し、上部構造である精神生活は経済生活に規定された存在に過ぎない、という考え方です。したがって、一見自由にものを考えているようでも、現実はその人の経済生活が精神生活を規定してしまっている。これを現代風に言えばポジショントークとなるわけです。
こうなると、その人が何を言おうが、結局はその人が拠って立つ立場や経済的な状況にすべてが還元されてしまい、会話が成り立たないという断絶が生まれます。
このような状況は近代においてますます深刻化しており、発言内容そのものよりも、その人の立場や状況から発言のすべてを判断してしまうことが往々にして起こっています。その結果、言葉や思想が交わることが非常に困難になってしまうのです。
内面性の追求と教育の重要性
しかしシュタイナーは、世界が記号化された言葉やイデオロギーに基づくコミュニケーションの断絶に終始するわけではないと言います。人間の本来の内面性は、経済生活に縛られたり、記号化された言葉に集約されたりするものではなく、もっと深いものがある。人間の精神は、記号化された言葉や経済生活を超えた何かを持っている、と。そこをシュタイナーは強く訴えたいのです。
そこでシュタイナーは、社会問題を考えるとき、結局は冒頭で述べたように「私の中の社会」を追求しなければならない、と説きます。私の内面にある社会衝動を見つめようとするとき、記号化された言葉や経済生活に拘束された精神を超えて、真の社会衝動に出会わなければ、本来の社会論にはたどり着かない、と問題提起しているわけです。
そうなったとき、精神問題としての社会問題に切り込む最も大事な糸口は何か。それが「教育」なのです。記号化された言葉や経済生活に束縛された精神から、私たちはどうすれば解放されるのか。それはまず教育によってしかありえないだろう、と。ここから、シュタイナー教育というテーマが立ち現れてきます。
このシュタイナー教育における最も根本的な原点は、「一人ひとりが絶対的に違うということを、肯定的に自覚する」ことです。これは当たり前のようですが、私たち一人ひとりの魂は絶対的に異なります。そして、その「異なること」を良しとする思想なのです。
まず、私たちの魂は一人ひとり絶対的に異なるということが、受け入れられなければなりません。これは、自分自身の日常生活を考えても、実は非常に大変なことです。私たちはややもすると同質性を求めがちです。特に日本は同質性の高い社会だと言われますが、その中で、一人ひとりが絶対的に異なることを認め、それこそが社会を構成する原点なのだという認識は、やはり教育を通じてでなければ育まれないのかもしれません。このような考えから、シュタイナーは教育論を展開していくことになるのです。
志村昌司(アトリエシムラ代表)による読書案内です。
主に文化、芸術、思想に関連する書籍を取り上げます。
youtubeでも毎週月曜日更新予定です。
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただければ幸いです。