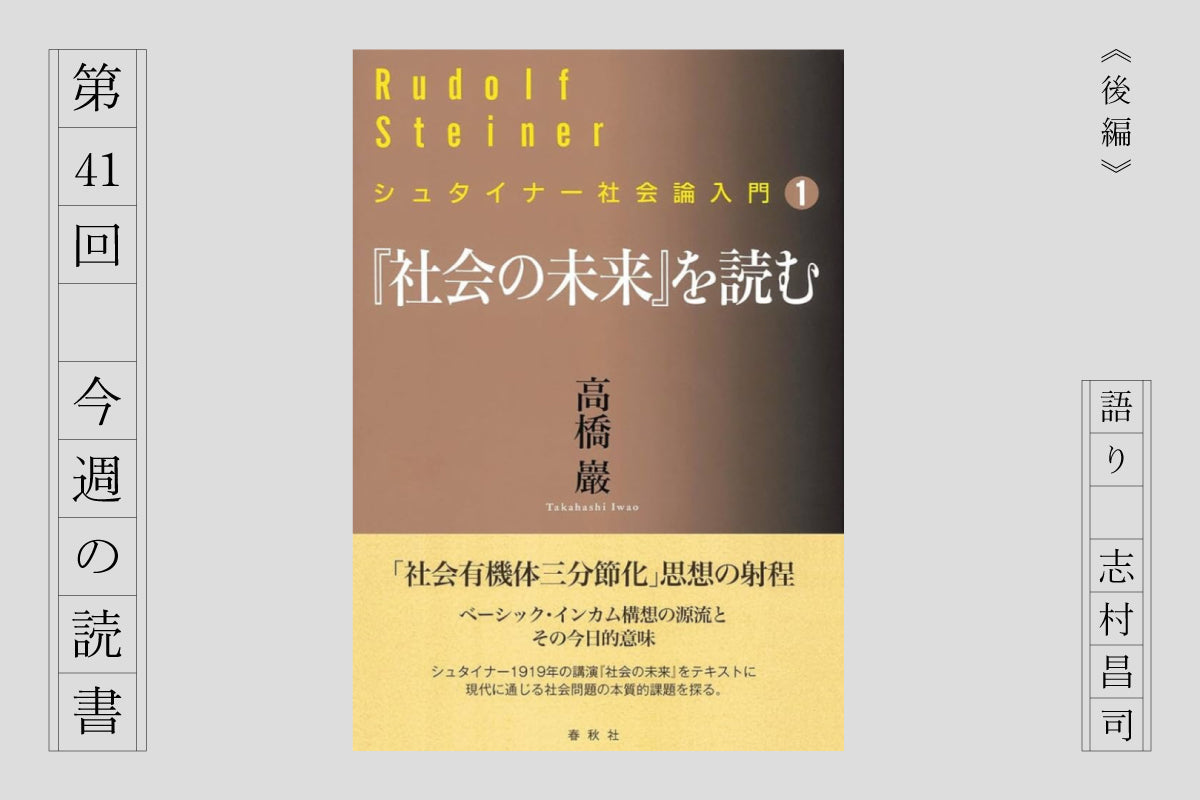
『社会の未来』を読む』《後編》
今週も、前回、前々回に引き続き、高橋巌氏のシュタイナー社会論入門『「社会の未来」を読む』を取り上げます。本書は非常に内容が深いため、このチャンネルでも3回にわたってお送りすることになりました。
今回は、シュタイナー社会論入門の最終回として、「社会有機体三分節論」の三つの柱である「経済生活」「法生活」「精神生活」について、シュタイナーの思想を解説します。
中編はこちら
1. 経済生活:労働力を商品化してはならない
まず、「経済生活」から見ていきましょう。経済生活には様々な側面がありますが、シュタイナーは特に「労働」の価値に焦点を当てています。
賃労働システムへの批判
現代の経済活動における労働とは、主に「賃労働」を指します。賃労働とは、自身の労働力を商品として販売し、その対価として資本家や企業から賃金を受け取る仕組みです。
この仕組みは現代では当たり前になりすぎて、逆に賃金を伴わない労働はあり得ないという風潮さえあります。しかし、数百年前まで遡れば、労働と賃金は必ずしも結びついていませんでした。現代でも、家庭内労働など、報酬が発生しない「隠れた労働」は数多く存在します。
シュタイナーは、この労働と賃金を結びつけること自体が問題だと指摘します。
「社会有機体三分節論」は、私たちの社会を一つの有機体(生命体)として捉える点に特徴があります。社会という有機体を健全に機能させるためには、「労働力を商品化してはならない」というのがシュタイナーの基本的な主張です。彼の言葉を借りれば、「労働を経済過程から完全に引き離さなければならない」のです。
労働は精神的行為である
なぜ、労働と報酬である賃金を切り離さなければならないのでしょうか。シュタイナーによれば、それは労働が本質的に「精神的な行為」だからです。それは金銭を得るためだけの行為ではなく、私たち一人ひとりが社会で行う精神的な活動なのです。
そして、この精神的な活動にとって最も重要な原則は「自由」です。私たちの精神的な自由を確保するためには、労働を賃金から切り離さなければなりません。
そうなると、現代の私たちには「労働が必ずしも報酬に結びつかない」「労働量と収入が比例しない」という状況を受け入れる、発想の転換が求められます。
ベーシックインカム(BI)論との接続
しかし、そう考えると、「どうやって生活したらいいのか」という当然の疑問が湧いてきます。労働力を商品としない新しい社会とはどのようなものか、私たちは考えなければなりません。
これは現代社会においても非常に難しい課題であり、労働と収入を切り離して考える社会はまだ実現していません。そこで注目されるのが「ベーシックインカム(BI)」という考え方です。シュタイナーの思想は、この現代のベーシックインカム論と接続可能なのです。
本書で高橋氏は、山森亮氏の『ベーシックインカム入門』などを参照し、現代のBI論を紹介しています。
キング牧師と「保証所得」
BIの思想は最近生まれたものではなく、古くから提唱されていました。高橋氏によると、1968年にアメリカの公民権運動の中でキング牧師が主導した「貧者の行進」というキャンペーンにおいて、彼が「保証所得」という考え方を打ち出したと言います。これがまさに、現代のBI論の先駆けと言えます。
保証所得とは、「全ての個人が、無条件で生活に必要な所得への権利を持つ」という、非常に明快な主張です。「全ての個人が、無条件で」という点が重要です。
生活保護のように条件付きで最低限の生活を保障する制度は多くの国に存在しますが、条件を撤廃し、全ての個人へ無条件で所得を保障する制度は、これまでほとんど実現していません。
例えば、日本の人口1億2000万人の一人ひとりに月額10万円を保障すると、単純計算でも月々12兆円、年間で144兆円という莫大な費用が必要となり、国家予算を超過してしまいます。
単純計算ではBIの実現は非常に難しいという結論になりがちですが、その実現方法については現在、様々な議論がなされています。
法制度や経済上の課題もさることながら、ここで重要なのは、BI論がどのような思想に基づいているかです。シュタイナーの観点から見れば、BI論の要点は、「労働と収入を切り離すことで、一人ひとりの精神活動の自由を保障する」という点にあるのです。
2. 法生活:感情の共有と平等の原則
次に、三分節の二つ目、「法生活」についてです。
この法生活において最も重要なのは「感情の共有」だとシュタイナーは言います。非常に興味深い指摘です。法律と感情は最もかけ離れているように思えますが、シュタイナーによれば、「正義の感情」や「これはおかしい」と感じる社会的な感覚こそが、法の源泉なのです。
法律は無から生まれるのではなく、その時代における国民的な感情が高まり、一つの法として結実した側面があるのです。つまり、法律はその時々の人々の正義感と不可分であり、法制定における大きな要因となっています。
民主的な手続きと「平等の原則」
ただ、一人ひとりの正義感は異なります。社会の中では、市民が抱く様々な感情がぶつかり合い、調整されていきます。多様な正義感が民主的なプロセスを通じて調停され、一つの法へと形作られていくのです。
その衝突を闘争や暴力に発展させることなく、議論を通じて円滑に発展させ、一つの法へと昇華させるための工夫が必要です。その工夫が「民主的な手続き」です。
そして、その民主的な手続きにおいて最も重要な原則が、「平等の原則」です。シュタイナーは、経済生活で最も重要な原則を「友愛」と呼びますが、この法生活における最重要原則は「平等」なのです。
平等の原則が働くべきなのは、人々が抱く様々な正義感が、等しく取り扱われなければならないという点です。そのプロセスが民主主義であり、シュタイナーもその過程において多数決の原理を認めています。
「理解可能」であることの重要性
この平等の原理を貫徹するためには、扱われる事柄が「人々にとって理解可能なもの」でなければならない、とシュタイナーは述べます。
社会生活には、構成員全員が原理的に理解可能な事柄と、個人の内面深くに関わる問題が存在し、これらは区別して考えられます。
個人の内面に関わる問題は「精神生活」の領域であり、そこでは平等の原理ではなく、「自由」の原理が適用されなければなりません。
法生活、すなわち社会における人々の正義感の衝突は、原則として誰もが理解可能な問題であるからこそ、各人の意見や感情が平等に取り扱われなければならないのです。
現実問題として、人々が平等に判断できる状況を作るためには、知る権利や報道の自由など、民主的な判断を成立させるための環境整備が不可欠です。単に議論の場があるだけでは、民主主義は成り立ちません。
法生活の独立性と「相互関心」
この民主主義(法生活)は、経済生活から独立しなければなりません。一つは、経済力によって意見の重みが左右されるべきではない、ということです。
もう一つは、精神生活からの独立です。これは、法が個人の内面にまで介入すべきではない、ということを意味します。シュタイナーは、民主主義は精神生活と経済生活の領域から独立しなければならず、その前提として「各人が、判断力において他者と対等な人間として向き合うこと」が条件になると述べています。
ここで、シュタイナーの非常に興味深い議論があります。それは、「社会に対する共通の関心を持つ」ことが、民主主義や法生活を機能させる上で重要だということです。つまり、自分の問題に相手が関心を持ち、相手の問題に自分も関心を持つという「相互の関心」が非常に重要なのです。
例えば、ワークショップなどで自己紹介を行うことがあります。一見、時間の無駄に思えるかもしれませんが、参加者の問題意識や背景を共有することで、「今、私たちは同じ場を共有している」という連帯感が生まれます。
この意識が共同体にあって初めて、民主主義は機能するのです。私たちが同じ社会の一員であるという意識を持つためには、互いに関心を寄せ、問題意識を共有する必要があります。この点こそ、もしかすると現代社会に決定的に欠けているものなのかもしれません。
3. 精神生活:「自由」「個」「沈潜」
最後に、シュタイナーが最も関心を寄せていたと言える「精神生活」についてです。この精神生活において最も重要な要素として、シュタイナーは「自由」「個」「沈潜(ちんせん)」の3つを挙げています。
「個」:集団ではなく個人として向き合う
まず「個」についてです。シュタイナーは、社会問題を扱う際には集団の立場ではなく、「個人(個)として考えなければならない」と強調します。
例えば、セクト(分派)や団体、法人が形成されると、私たちはその集団の立場で物事を考えてしまいがちです。個人から離れた「団体としての立場」から社会問題に向き合うと、問題の本質が見えなくなってしまうというのです。
シュタイナーは、そもそも社会問題に取り組む際には、「私の中の社会」からスタートすべきだと説きます。つまり、出発点は「私が所属する団体の理想」ではなく、「私自身はどのような社会を理想とするか」という個人の内なる社会意識でなければならないのです。この点を徹底しなければ、結局は分派間の対立やセクト主義に陥ってしまう、とシュタイナーは強く警告します。あくまで個人として、主体的に向き合わなければなりません。
「自由」:内なるものを目覚めさせる
次に、「自由」とは何か。シュタイナーは、人間が生まれながらにして自由な存在だとは考えていません。むしろ、私たちの内面に「まどろんでいる何か」を目覚めさせ、発展させることによって、初めて自由な存在になるのだと考えます。これが『自由の哲学』における基本的な考え方です。
これは「人間は自由か否か」という問いではありません。私たちの内的な発展を通じて、人間は自由な存在に「なり得る」というのがシュタイナーの基本的な主張なのです。
自由になろうとするなら、まず自分自身と向き合わなければなりません。自分自身と向き合い、内なる可能性を目覚めさせ、育んでいく。そのプロセスを経て初めて、私たちは真に自由な存在となり得るのです。
そのためには、様々な外的制約から解放され、まず自分自身が精神的な自由を獲得することが不可欠です。精神生活における最も重要な原理が「自由」であるというのは、まさにこの内なる可能性を解き放つことの重要性を示しているのです。
「沈潜」:相手の中に深く入り込む理解
三つ目の「沈潜」は非常に興味深い概念で、本書で高橋氏がシュタイナーの言葉の中で最も重要だと指摘する部分です。
「私たちが社会の中に生きるとき、悪しき人類とともに悪しき人にもなれる才能を発揮できるということが大事なのです」
これは難解な言葉です。この世に善悪の問題があると仮定したとき、社会問題を解決するためには、この「悪」と向き合い、悪の中へも沈潜していける人間であることが非常に重要なのだとシュタイナーは言います。
これはシュタイナーの思想によく見られる考え方です。相手を理解しようとするとき、決して自分の土俵に引き寄せて考えてはならない、と。そうではなく、自分自身が相手の中に入り込み、自己が消えるほどに融合する経験がなければ、真の理解には至らないと言うのです。そのことをシュタイナーは、「相手の中に深く沈潜していく」と表現します。
たとえ相手が「悪しき人間」であったとしても、まずその内面に入り込み沈潜していく。それによって初めて見えてくる世界があるというのです。
それは、私たちが普段考える知識や教養とは逆のベクトルを持つものだとシュタイナーは言います。知識や教養が外へ外へと広がっていくものであるのに対し、真の理解(シュタイナーの言う霊学的な理解)とは、内へ内へと深く沈んでいくような、相手の世界に没入していくようなあり方なのです。
したがって、たとえそれが悪であったとしても、一度その中に深く身を沈めてみなければ、社会における悪の問題は解決できない、とシュタイナーは説いているのです。
おわりに
このように、精神生活においては「自由」「個」「沈潜」の三つが重要な柱となります。
シュタイナーの社会論を3回にわたってご紹介しました。シュタイナー独自の認識論から展開される社会論は、従来の社会論とは一線を画しており、驚きを感じる点も多いかもしれません。しかし、これからの混沌とした時代を生き抜く上で、非常に示唆に富んだ視点を与えてくれるはずです。
ぜひ本書『『社会の未来』を読む』や、シュタイナーの原著を手に取り、思索を深めていただければ幸いです。
今週もご視聴いただき、誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。
志村昌司(アトリエシムラ代表)による読書案内です。
主に文化、芸術、思想に関連する書籍を取り上げます。
youtubeでも毎週月曜日更新予定です。
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただければ幸いです。